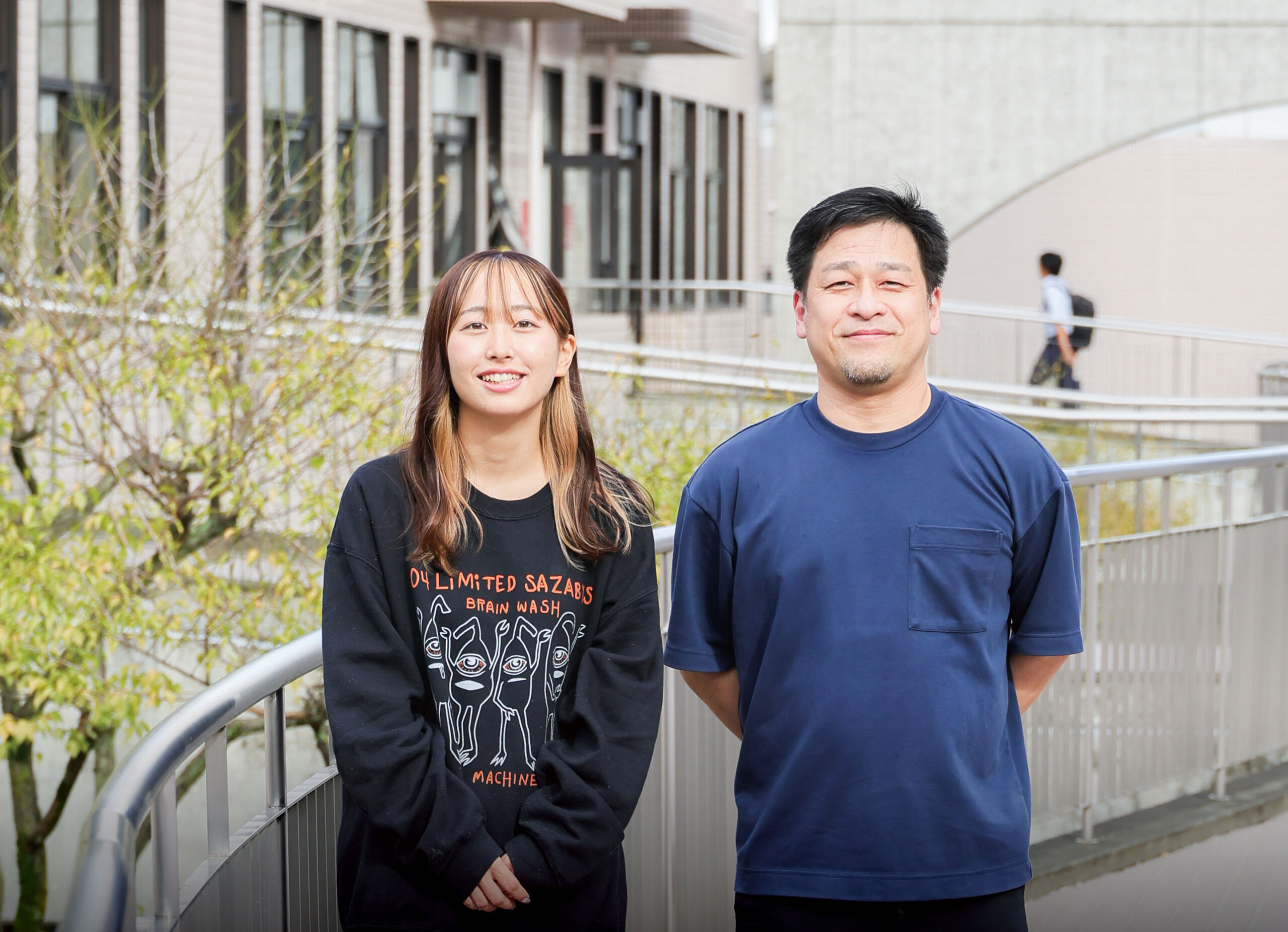どんなタイプの人でも安心して学べる大学。それが嘉悦大学です。
大学生が自己成長するにあたって欠かせないのが「研究会(ゼミ)」です。自分がどのゼミに入るかによって大学生活での成長度合いが大きく変わるため「ゼミの選び方」がとても大切です。自分に合ったゼミに入ることができれば、卒業までの大学生活をいっそう充実させることができるでしょう。「興味がある研究ができる」、「ゼミの研究実績が高い」、「教授の評判が高い」、「ゼミの雰囲気がよい」など、ゼミを選ぶ観点はさまざまです。外に飛び出して多くの人と出会いたいという人もいれば、教室で静かにコツコツと勉強したい人もいるでしょう。嘉悦大学であなたにジャストフィットするゼミを見つけてください。
多彩なゼミ(研究会)が充実!
ワクワク活動したい人向き/岩月基洋ゼミ ―地方創生―
音楽と経営学、私のユニークな歩み
小学校から高校まで吹奏楽部に所属し、高校では部長として組織をまとめることも楽しんでいました。経営経済との出会いは意外でしたが、上京することで大好きな吹奏楽を続けられると考え、嘉悦大学を選びました。音楽系大学にも進もうかと思いましたが、高校の先生から「君の未来はプロ音楽家か音楽教員だけじゃないよ」と言われ、えっ、そんな世界もあるのかと気づいたのです!今のうちから進路の幅を狭くするのではない、汎用性ある経営学や経済学に興味がわきました。
岩月ゼミでの「課題探し大冒険」
岩月ゼミを選んだのは、マーケティングや商品開発がチラチラと頭に浮かんだのと、地域活性化センターとの連携で、地域の課題を見つけ出すのが面白そうだったからです。岩月先生は「自分で考えて動け!」スタイル。指示は少なく、現地に飛び込んで自分たちで課題を見つけるのがルールです。地域課題に関しても、ステレオタイプを押し付けず、ゼロからイチを作るこだわりがあって楽しいです。
ゼミ生の視点も十人十色で、私が山形出身ということもあって、首都圏出身者の「何も無い地域が価値?」という発見は、まるで目から鱗でした。地域活性化の成果より、自問自答を繰り返しながら、自分が何者で、何をしたいかがクリアになってきたのを実感しています。卒論では、地域の吹奏楽文化を絶やさないアイデアを探る予定です。地域の方々に「リラックスして楽しんでもらえる」吹奏楽のアイデアを模索中です。
地域活性化と心の化学反応
私のゼミは「地域活性化」をテーマにしていますが、新聞やテレビでおなじみの「少子高齢化」「インフラの弱体化」「経済活動の衰退」といったメディアを賑わすテーマを掲げてなにか魔法のような解決策を求めるわけではありません。むしろ、学生たちが地域の現場に立ち、地域の人々と関わる中で「なんでこんなことが?」という想定外の気づきや、地域の課題にどうアクションを起こすかを一緒に考えています。
ある地域のAさんは「これをやって!」とリクエストするけど、Bさんからは「いや、それはやめて!」と言われることも。こうした矛盾やちょっとした理不尽さにどう向き合えばいいのか、そこが面白いのです。学生が地域とリアルに関わったときに生まれる心の化学反応を大切にしています。ゼミ活動は、二十歳前後という若者たちが何かを動かそうとする過程そのものが学びであり、貴重な体験なのです。
努力とちょっとした無謀さ
地域社会にすぐに役立つなんてことを考えるのは急ぎすぎです。もちろん、4年次に「卒業制作」という集大成がありますが、「地域活性化」は一朝一夕に解決できるものではなく、情勢は常に変わります。日々の積み重ねがカギです。
最近、ゼミの卒業生がお笑いの養成所に入って、M-1グランプリで一回戦で敗退した話を聞きました。彼は元気そうで、悔しそうでもある(笑)。でもきっと彼は自分の頭で考えて、次の一歩を踏み出すことでしょう。私が何かを教えたわけじゃありません。彼自身が自分の生き方を見つけ出したのだと思います。
冷たい教員かもしれないけれど(笑)、私はいつも対等な大人として学生に接しています。自分で考え、主体的に動くことが大切です。そして、答えがない「地域活性化」にはそんな面白さと可能性があるのです!
コツコツ勉強したい人向き/飯野幸江ゼミ ―会計学―
会計学と私のデビュー戦
私が学んでいる会計学のゼミは、元気いっぱいなフィールドワークをするゼミとは対照的に、静かに財務諸表を読み込むスタイルです。でも、心強い味方がいます!飯野幸江先生が、私たち学生のために優しく寄り添ってくれて、難しい会計用語や堅い法律もなんとか理解できるように分かりやすく教えてくれるのです。
私の思い出の1年次、必須科目の簿記入門授業では、対人コミュニケーションが苦手な私に対して、飯野先生はまるで温かいお茶のように優しく接してくれました。ゼミ説明会では、他の会計ゼミも資格を重視している中、飯野先生の指導とゼミの雰囲気が私にはぴったりだと感じ、ここで学ぶことに決めました。
法律の学びと新たな興味
2年次では、会社法や金融商品取引法といった法律の勉強が中心で、正直言って時には退屈に感じることもありました。しかし、3年生になり、企業のリアルな財務諸表を読むうちに、ケーススタディは一気に現実味を帯びてきました。イメージが良い大企業でも実は経営が危ういことがあるなんて知って驚きましたし、反対に、零細企業が利益を出していることを知って、身近な街の景色が全く違って見えるようになりました。
もともと義兄が税理士なので、その影響で会計学の道を選びましたが、飯野ゼミで様々な企業の裏舞台を知ることで、今ではIT業界への就職にも興味が湧いてきました。人前で話すことに挑戦したくて、学生広報部にも応募しました。
高校でも教師と話すのにドキドキしていた私が、今では嘉悦大学で教員と親しくコミュニケーションをとれるとは、自分でもびっくりしています。きっと誰でも、少しずつ話せるように成長できると思います。
ゼミ生同士で緩やかにつながり、じっくり考えましょう
会計学への静かなアプローチ
私の会計学ゼミは、口数が少なく一人で勉強するタイプの学生が多い、まるで静かな図書館の中のようです。他のゼミから移ってくる学生もいて、「前のゼミの雰囲気、どうもフィットしない…」という声が聞こえてきます。今どきの学生は、対人コミュニケーションが個性に依存しているので、その子が居心地の良いと感じるゼミを選ぶのが最善策だと思います。
「会計学」という言葉を聞くと、日商簿記や税理士、公認会計士の資格勉強をイメージする方が多いですが、このゼミの最終目標は少し違います。学生が会計というツールを使って会社や社会の問題を見つけ出し、その解決法を自分で考える力を育むことにしています。資格取得については希望者には、別のカリキュラムを用意しています。
会計で知る柔軟な学び
3年間の勉強は、2年次で基礎知識を学び、3年次には企業の財務諸表を分析や評価をします。そして4年次にはその集大成として卒論が待っています。毎回、課題を出してそれをクリアすると、学期末にはレポートが完成する仕組みにしています。一見一人で完結するように思えるレポート学修も、実は学生同士でGoogleドキュメントを使って全員のレポート情報を共有しているのです。これで、静かな中でも緩やかにつながり、他の学生の視点を学ぶチャンスが生まれます。
会計学は決して経理担当だけの学問ではありません。すべての企業には会計が必須で、営業部や広報部でも役立つ知識です。取引先の企業分析やIR発信に必要な知識も含まれ、汎用性が高い学問です。じっくり考えて掘り下げていけば、興味はどんどん増えてきます。コツコツ型の学生にはまさにうってつけの学びの場ですね!
多彩なゼミで仲間と一緒に色々なことにチャレンジし、自分の可能性を開く。
森本孝学長
昭和38年(1963年)兵庫県生まれ。慶應義塾大学経済学部卒業。慶應義塾大学経済学研究科後期博士課程単位取得退学。経済学修士。1992年、嘉悦女子短期大学(現、嘉悦大学)に着任以降、一貫して「人材育成を通じて社会に貢献する実学の府」という創立者の理想の実現に邁進。経営経済学部教授、経営経済学部長歴任後、令和5年(2023年)4月より学長。専門は経済学史、経済思想史。
嘉悦大学は学生の皆さんの「挑戦」を何よりも大切にする大学です。そうした嘉悦大学の教育の中心がゼミです。嘉悦大学の学生は全員、2〜4年生の3年間、少人数のゼミで学びます。ゼミは殆どの大学にあります。では嘉悦大学のゼミの特徴はどこにあるのでしょうか。それはその多彩さにあります。他の大学と同じく、経済学や経営学という学問分野で自分の研究課題を決めて学術論文を作成するという「学問」的なスタイルのゼミももちろんあります。しかし、それだけではなく、簿記・会計、データサイエンス、ビジネス法務などの資格を目標に「実務」の能力を磨くゼミや、地域社会や企業などの現場に飛び出して、現場での「実践」を通じて社会やビジネスの課題の解決に取り組むゼミもあります。嘉悦大学では、「学問」だけでなく、「実務」「実践」の面でも、学生の皆さんにたくさんの「挑戦」の機会を用意しています。ゼミで仲間と共に色々なことに挑戦し、仲間と共に成長し、自分の可能性を開いていって欲しいと思います。
嘉悦大学の研究会(ゼミ)一覧
24もの研究会(ゼミ)があり、1年次に学んだ基礎知識を基に2年次から学生が自らの眼で選択していきます。